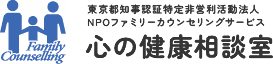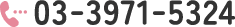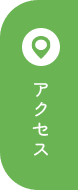体験型相談週間
ピンチはチャンス! 少しの勇気で人生は変わります。お気軽にご相談ください。
- カウンセリングを受けたいが料金が高い
- どんなふうにやるのか知りたい
- どんなカウンセラーなのか分からないと不安
- ほかでもカウンセリングを受けているが、比較してみたい
こう思っている方は沢山いらっしゃいます。
そういう方にも安心して、より多くの方にカウンセリングをご利用いただけるよう、毎月サービス週間を設けております。
(4月のサービス週間はご好評のうち終了しました)
5月のサービス週間
3日(金)~12日(日)
午前9時~午後7時 (ご相談に応じます)
60分 3000円
毎月大好評で多くの方が申し込まれます。なるべく沢山の方にこのサービスをご提供するために、
初回1回のみのご利用とさせていただいておりますので、ご了承ください。
- 個別相談(60分)3000円
- 複数同時カウンセリング(お二人以上の場合)は、90分 6000円
- カウンセリングの内容は、平常の有料相談(60分 6000円)とまったく同じです。
- 要予約。ご希望者がとても多いので、早めのお申し込みをお勧めします。
- 当日のお申し込みですとお受けできないことがありますので、前日午後5時までにご予約をお願いいたします。
- 他に情報が漏れることは絶対にありませんので、安心してお話ください。
- サービス週間では担当カウンセラーのご指名は出来ませんので、予めご了承ください。
- 海外に住んでおられる方も、電話カウンセリングとしてご利用いただけます。