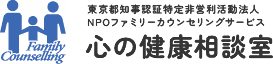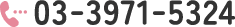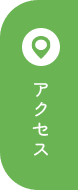お悩みの内容に拘わらず、何らかの事情で相談室へいらっしゃるのが困難な方の場合、引きこもっている状態の方、外出に不安がある方などにご利用いただいています。また、地方にお住まいの方の場合は、お電話でのカウンセリングも喜ばれております。
対面カウンセリングでも使う、カウンセリングシートをカウンセラーと相談者の間で丁寧にやり取りすることにより、直接お会いするカウンセリングにほぼ匹敵する効果が得られています。
事例1
40代女性 電話カウンセリング暦6ヶ月
離婚後、うつ状態になり、自信も失くし、これからの人生をどう生きていったらよいか全くわからない状態で電話カウンセリングを開始。
シートを使ったカウンセリングを通し、次第に自分の持ち味を感じることが出来るようになり自分を認められるようになった。また、アサーションの練習・実践をすることで身近な人との状況が改善し、これからの人生に希望が持てるように回復。
事例2
30代男性 電話カウンセリング暦1年
自営業。従業員との人間関係がうまく行かないため、毎日が辛く、店に出るのが苦痛に。いつもびくびくしてしまい、食欲不振、不眠などの状態も。当初、電話カウンセリングには不安があったが、シートを使ったカウンセリングを通して、「自分は無理しすぎていたこと、自分らしくいれば充分通用すること、少しだけコミュニケーションの工夫をすればよいこと」が分かり、マイペースと体調を取り戻し、しかも従業員との関係も改善された。